最近よく耳にする「サステナブル」という言葉。
実は、その考え方を昔から実践してきたのがパーマカルチャーと自然農です。
両者はとても似た哲学を持ち、目指す方向もほとんど同じ。
今回は、それぞれの概要と歴史、そして私が感じた魅力をまとめます。
パーマカルチャーとは?

ひと言で言えば、「自然と人が共に豊かになる持続可能な暮らしのデザイン」です。
農業だけでなく、住まいや地域社会のあり方まで含めた広い概念ですが、雑草や虫を味方につける考え方は自然農とほぼ同じです。
パーマカルチャーの3つの倫理
- 地球への配慮(Care of the Earth)
地球なくして人は生きられないという前提のもと、環境を守る。 - 人々への配慮(Care of People)
人が生きていくために必要な資源を確保し、支え合う。 - 余剰物の共有(Fair Share)
奪い合うのではなく、余剰を分かち合う。
12のデザイン原則
創始者のひとり、デイヴィッド・ホルムグレンが提唱した原則です。
- 観察と相互作用
- エネルギーの獲得と貯蓄
- 収穫
- 自律とフィードバックの活用
- 再生可能な資源の活用と尊重
- 無駄を出さない
- 全体からディテールをデザイン
- 分離より統合
- ゆっくり小さな解決を目指す
- 多様性を活かす
- 接点や辺境の価値を尊重
- 変化に創造的に対応
難しく聞こえるかもしれませんが、要は「自然と人が共生する仕組みをつくる」ということです。
(「森とタタラ場、双方共に生きる道はないのか!!」by アシタカ…まさにそんな感じです)
パーマカルチャーと自然農の歴史
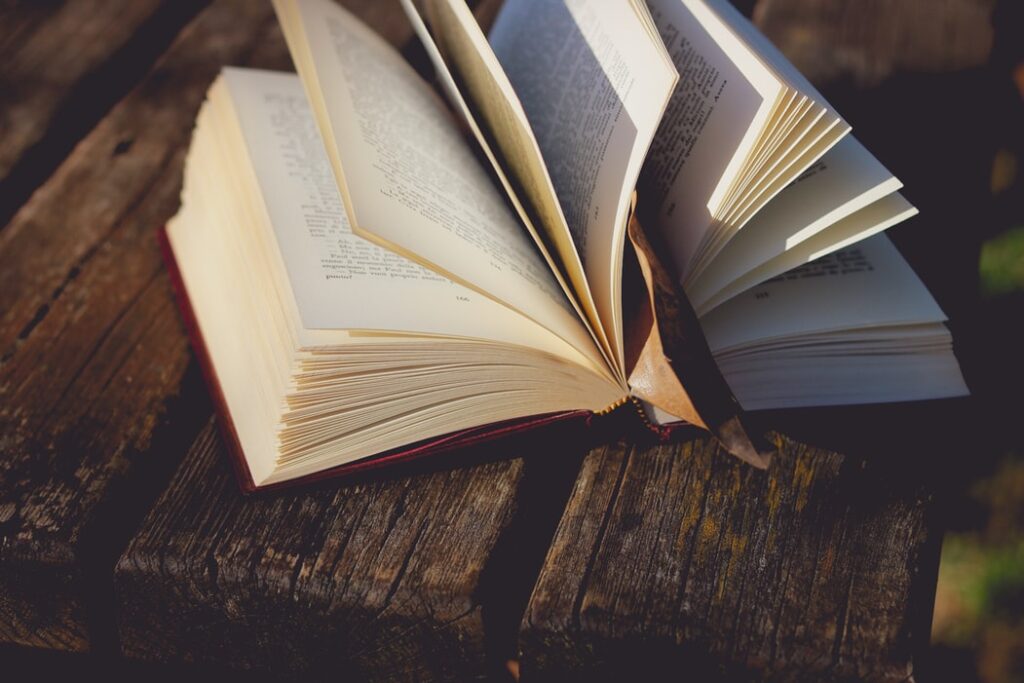
パーマカルチャー
1970年代、オーストラリア・タスマニア島でデイヴィッド・ホルムグレンとビル・モリソンが提唱。
「Permanent(永続的な)」+「Agriculture(農業)」の造語です。
自然農法
日本では岡田茂吉氏と福岡正信氏が代表的な提唱者。
- 岡田茂吉氏
1936年に自宅庭で野菜栽培を試み、1950年に「自然農法」と命名。 - 福岡正信氏
1937年から実験的に自然農法を開始。1947年以降、不耕起・無農薬・無肥料・無除草を基本とする方法を確立。
著書『自然農法 わら一本の革命』は世界各国に翻訳され、国際的に影響を与えました。
時系列的に見ると、日本の自然農法がパーマカルチャーに影響を与えた可能性もあります。
私がパーマカルチャーに惹かれた理由
自然農に憧れて家庭菜園を始めましたが、野菜だけでなく果樹やハーブも育てたいと考えていました。
そんな時に出会ったのがパーマカルチャー。
果物、ハーブ、野菜を組み合わせ、畑そのものを心地よい空間にデザインするという考えに惹かれました。
(「ポタジェガーデン」も似た発想かもしれませんね)
「地球を森で覆い尽くす」というビジョン

ビル・モリソンは、パーマカルチャーの目的を「地球を森で覆い尽くす」と表現しました。
この言葉を聞くと、『風の谷のナウシカ』を思い出します。
ナウシカの世界で「腐海」は大地を浄化し、虫たちはその役割を守っています。
自然農も同じく、虫や雑草を敵視せず、土を豊かにする仲間として共生します。
これから目指すこと
パーマカルチャーは農業の方法論を超えた、大きな世界観です。
ですが、その中の農業部分は自然農とほぼ一致しており、目指す場所も同じ。
私は、自然農の実践にパーマカルチャーの考えを加え、多様性に富んだ畑を作りたいと思います。



コメント